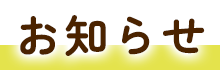あなたのまわりにモノマネ上手な人はいますか?
私にはいます。食べ物を見つけて喜ぶチンパンジーとかが秀逸です。
どうも、田中です。
英語専門外(とはいえ、義務教育課程まではできます)の私にしては珍しく英語タイトルにしてみましたが、日本語としての意味は名詞だと「同上・同断・同じこと」、副詞で「同様に」と取ります。
語源はイタリア語の「前に言った」という意味でのprima ho dettoからきているようですね。
口語英語のスラング表現であり、I love you.の返しで使うともれなく相手側から不満げな顔をされるので使わないようにしましょう(大事なことはちゃんと表現しろ、というのは万国共通です)
実はこちら、西洋でのポケモンのメタモンの名称でもあります。
メタモンは他のポケモンに変身するモンスターですが(育て屋に片割れで預けると、どのモンスターとも卵ができるってネタが通じる人は同世代)、ゲームを西洋にローカライズする際、子供たちがキャラクターにより共感してもらうため、様々なポケモンの種類にその見た目や特徴に関連した「巧妙で説明的な名前」がつけられているそうです。
言語の違いでキャラクターの名称をかえていく努力を怠ると、とんでもないことになっちゃいますからね。日本ではポケットモンスターでなんら問題ありませんが、海外だとアレなワードになるのでPOKEMONとしか言われませんし、カルピスも海を渡るとカルピコですからね。英語圏だとカウのピーに聞こえるとかの理由で。
言語間の面倒話は置いといて、「模倣」は全てにおける第一歩です。
人間は幼少期から大人になるまで、いかに模倣上手であるかによって可能性が広がっていきます。
生まれたときに備わっている本能から、身体を上手に使って模倣を重ね、それと同時に脳を発達させることで人はお箸を使って食事をとれるようになります。
もちろん、その模倣には教える側の手助けが必要なことも多くあり、例えば「左利きだから何教えるにしても面倒だからほっとけ」とかやってしまうと、正しい箸の持ち方ができない大人になってしまうのです。恐ろしや。
恥をかくのが全部教えなかった側になればいいのですが、残念ながらそうはなりません。不幸は全て「下」に降りかかるもの。
幼児教育においてダンスが注目されるようになったのも、この模倣の能力を伸ばすためですね。リズム感や表現力、協調性、運動神経などを育み、身体の柔軟性だけでなく思考の柔軟性を育むともいわれますが、その全ての源に模倣があります。
水泳にしても、体操にしてもDittoですね。
勉強ではどうでしょうか。
いわゆる基礎というものは、全て模倣であり、新たな模倣の源です。
知らない言語を調べること、調べる方法、調べてから出てきた意味を理解すること、その言葉を使ってブログを書くこと。
何もかも模倣からスタートです。
知らない言葉が出てきたら、調べることを習うのは小学校ですね。調べ方は人から習うものです。もっといえば、幼少期に聞いたことのない言葉を聞いたときに人に教えてもらい、同じような使い方をするのは完全に模倣です。
国語辞典での意味調べが英単語の辞書引きの元であり、品詞の理解がなければ意味も理解できません。品詞の理解も国語での模倣から始まって、詳しい理解は小・中学校で習うもの。
理解した言葉を使って表現することも、多くの先人たちが残してきた文章として形にすることを模倣しているに過ぎません。
模倣を通じて人は脳を発達させ、様々なものを進化させてきました。
ゆえに能力が高い人=模倣が上手な人になるのです。
出だしで伝えたチンパンジーものまね友人は、ダンスがお上手であり、また他人の癖をよく見ています。観察眼が鋭いこともまた、人より多くの模倣がある証拠ですね。
未経験ばかりだと人間の脳みそはすぐにパンク(覚えられない)状態になりますが、すでに経験していることに対しての受け入れは容易であり、数多くみてきた他者との比較によって癖を見抜くのです。
さて、GWも後半になりました。
塾はお休みとなっていますが、時間を無駄にせずに模倣の経験値を積み重ねていますか?
これは全て勉強の時間にしろと言っているわけでなく、遊びでも部活でも何でも構いません。こういう時だからこそできることを個人的にはすべきだと思っています。
人生の糧となる新しい経験、珍しい経験、模倣をさらに研磨する経験、あなたはしていますか?
そして授けていますか?
偉そうな立場での物言いになってしまいますが、授ける側の働きがなければできない経験が多くあることも事実です。
GWに普段はほとんど接することのない父親と2人でスキーに行くことが、私にとっては印象深く覚えている経験の1つです。
こんな時期でもスキーができる楽しみ、人を待つというストレスなくハイスピードでゲレンデを滑れること、普段乗ることのない車の助手席に乗るのが許されること、温泉に入ったあとに食事をして帰ること。
嬉しかった経験のベースを模倣して、今ではそれを提供する側として卒塾生たちを連れまわしています。
連れまわされている側が何を思っているのかは知りませんが、普段も休日も、良き模倣を提供できるようこれからもやっていこうと思う、5月5日子どもの日でありましたとさ。