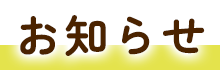だめな行為がかっこよく見えることがありましたか?
私はありました。
だめな先輩たちを見習って作り上げられた人間のたなかです(人のせいにするな)
だめな行為の代表例と言えば、ひと昔前の未成年の喫煙や飲酒があげられますが、そういったことよりももっと前の話です。
なぜか小さい頃、何となく真似したい行為がありませんでしたか?
今となっては馬鹿としか思えないのですが、私は貧乏ゆすりを真似したいと思っていました。
真似して実際に行動に移して、速攻母親の怒号が飛んできたので二度とやらなくなりましたが(笑)
真似をしたくなるというのは本能的な行動であり、成長や学習、憧れ、仲間意識や社会性の獲得、自信の獲得、そして安全志向に分類されるようです。
恐らく私の場合は、貧乏ゆすりをしていた父親でも見ていたのでしょう。1番身近な共同体の父親という存在がおこなっていた「悪しき」習慣を、善悪の判断なく真似たかったのだと思います。
これは成長の過程上仕方のないことであり、大事なのはその後です。
良し悪しの判断のできる大人がしっかりと気付いて注意できるかどうかは環境の問題ということになるでしょう。
怒号が良いかどうかは知りませんが、だめなものはだめだと教えていただいたことだけは感謝しておこうと思います。
礼儀やマナーというとうるさい専門家的な連中が過剰に反応するのが目につきますが、椅子に座ったときの正しい姿勢、様々な立ち振る舞いの所作など、古来より「美しい」とされているものは決して蔑ろにするものではないと思います。
「美しい」状態は最初から美しいまま生まれてきたわけではありません。
赤ん坊は椅子に座ることはできませんが、成長していくにつれて椅子に座ることを覚え、姿勢を正すことを覚えていくものです。足を組んだりブラブラしたり、貧乏ゆすりをしたり、椅子に足をあげたりといった悪しき習慣を諫められながら、「美しい」状態を作れるようまわりがサポートしていくものです。悪しき習慣を何でも許す多様性の社会なんてものは、少なくとも私は望んでいません。
咳払い、鼻水啜りなども真似によって身についてしまう悪しき習慣ですね。
病気で咳が出てしまうのは仕方ありませんが、咳払いして話し出すことは決してかっこいいことではないと言ってあげないと、授業中に邪魔するように咳払いする小学生になってしまいます。
鼻水もすすり続けると蓄膿症になってしまいますが、小学生はまわりも啜ってるから、鼻をかむのが恥ずかしいから、などの理由で流されがちですね。
習慣は生活の端々で出るものです。私自身も良くない部分が多い人間ですが、直してほしいと思っている人間(ここ重要)には伝えるようにしています。
どうでもいい人間もどきには何も言いません。「事なかれ主義のたなか」ですから、そのあたりは昔より面倒ごとを恐れて注意をしなくなった学校の先生方と同じスタンスのしょうもない存在ですね。自覚しております。
小さい頃は失敗の日々ですが、その中でいかにまわりが気付いてあげられるかが大事だと思います。
手がかからなくなったと思う小学生でも、筆箱1つ見れば多くのことがわかりますよ。
・持ち手のところや真ん中あたりが妙にへこんだりかすれている鉛筆←かじってます
・欠けてぼろぼろになっている定規←通称じょうせんやってます
・砕かれた消しゴム←手持ち無沙汰で暇つぶしで破壊してます
・ノックが押せないボールペン←ばらしてバネ飛ばして無くしてます
・異様にインクの減りが早いカラーペン←髪の毛に色つけてます
道具には様々なストーリーが残りますからね。
自分も通ってきた道のりなので、別に否定はしません。子どもの休み時間のユニークな創造や破壊から学ぶこともありますから。ただ1つの見方としてちゃんと諫めてくれたり、早い段階で物の大切さを教えてくれたりした共同体の誰かが、私の近くにいたことには感謝したいですね。
多様性を何でもありとは捉えたくない、時代の波に逆らっている老害偏屈側の徒然なるままに、でした。