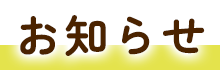書籍を出版した友人をもっていますか?
私はもっています。どうも田中です。
ちなみに書籍はこちら。ぜひ買って読んでみてください。
https://www.amazon.co.jp/dp/4413234030やわらか仏教

塾生には特別にお貸ししますので、借りたい人は獨協大学前本校の本棚を漁ってくださいね。
著者は兄弟のお坊さん。お兄さんの方は同い年なのですが、ほとんど面識がなく、1度か2度お寺で顔を見たことがあるくらい。友人にあたるのは2つ年下の弟の方です。
そもそもお坊さんが友人というのがレアですが、最初からお寺の子として知っていたわけではなく、アルバイト先の先輩と後輩(私の方が後から入りました)という関係でした。
あまり自分と関わらないでくれオーラ全開の私とのファーストコンタクトの際、逆に絡んでやろうと弟坊主は思ったそうで。
2年遅れて大学に入った私と現役大学生だった弟坊主は大学の学年としては同じであり、そこからはなんやかんやで遊ぶようにもなり、一時期は東京の中野区でルームシェアをしたり。
今ではお互いに忙しい身となってしまいましたが、誕生日が近いことから恒例のプレゼント交換は欠かさずにおこなう、不思議なご縁となっております。


宗教が絡むとマイナスのイメージを持つ方も多くいることでしょう。ですがこの国に住んでいる以上は、何らかの宗教に必ず接しているともいえます。
日本人は無宗教ともいわれますが、元旦もお盆もクリスマスもある国は無宗教ではなく、「何でも教」の国です。
教育に関しても宗教は多くの部分で影響があります。
上智、立教、青山学院、同志社、英語系で名前が売れてる大学はそのほとんどがキリスト教がらみ。ICU(国際基督教大学)なんて思いっきりそのまま。獨協も宗教専門教育こそおこなっていませんが、ドイツ系の学問からスタートしている以上、当たり前にキリスト教の精神に触れることになります。
キリスト教系の大学はいずれも明治期以降に設立されたものですが、仏教系の大学の方が歴史は長いです。歴史的背景として関西の方が仏教系大学は多くあり、たとえば四天王寺大学はその起源を聖徳太子の時代にまで遡れますし、龍谷大学も1639年に西本願寺境内に作られた学寮が起源になっています。関東では曹洞宗を淵源とする大学として駒沢が有名ですね。1592年の学林がその起源となっています。
元々は僧侶養成に重点が置かれていましたが、次第に信徒の教養教育、技芸教育にも力を入れるようになり、「寺子屋」と呼ばれる民間教育機関を併設するところも出てきました。これらの教育のノウハウが一般の人々からも支持されるようになり、大学とその付属高校、中学校を擁する学校法人にまで発展したところもあります。
とまあ、真面目な話はここまで。
別に弟坊主のことは最初から寺の息子として付き合ってきたわけでもないですし、人間的にcrazyでおバカな付き合いも多々。私が入院したら法衣姿で見舞いにくるやつ(看護士の人たちがざわつくのも無理はない…)
でも仕事になればやるべきことをちゃっちゃと済ませたりと、人として何かしら魅力があったからこそ今でも付き合いがあるのだと思います。
恐らく、お坊さん界隈の中でも変なやつなんでしょう。兄弟でラジオ配信とか、思いついて行動に起こすやつはなかなかいませんよ。
書籍だって出そうと思っても形になるまでに越えなければいけないハードルは多い。それでも何か面白そうだからって考えて行動できる。オールドメディアだけでなく、SNSもちゃんと使いこなす。
トライ&エラーを繰り返し、ブラッシュアップしていく。様々に考え、行動をおこすフットワークの軽さ。見習うべきところが多い年下です。
面白い人間との出会いは、私の1年以上の流浪と大学に行く4年間の時間を買わなければ、なかったことでしょう。人と人との不思議な巡り合わせはご縁としか言いようがないですが、そのご縁を引き寄せるのは自分の行動です。
ということで、夏が始まります。
関東のお盆は実は7月。弟坊主はさぞ忙しいことでしょう。
我々も受験に向けてしっかりと勉強時間が取れる夏休みが始まります。
お互いに暑さで干からびないよう、がんばっていこうと思う今日この頃でありましたとさ。