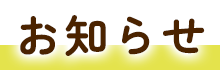最近の子って恐ろしいなと思いました。どうも東出です。
前回のブログ記事にて、私がYouTubeでの動画配信を趣味でやっていることを記事にしたのですが、なんとうちの生徒に見つかってしまいました。それも二人も。
ゲーム実況というジャンルだけバレてて顔出しもしていないのに、どうやって見つけたんでしょうか。
ある日「東出さん〇〇(チャンネル名)って知ってますか?」と聞かれて震えましたね。
お二方よ、そんなことに時間を使う暇があるなら勉強してくれ(笑)
…デジタルネイティブという言葉が使われるようになって久しいですが、今の中高生はまさしくこの世代。
生まれた頃から親がスマホを使い、テレビよりも動画配信サイトを楽しみ、わからないことは当たり前のように検索エンジンで調べる世代です。
彼ら彼女らにとって、自分の知りたい情報を見つけられることは当たり前のことですが、それは決して「調べる能力が高い」わけではなく「調べる過程の多くを検索エンジンが排除してくれているから簡単なだけ」だと私は解釈しています。
自分のわからないこと、知りたいこと、情報を調べるプロセスは以下のような5段階にざっくりと分けられます。
【情報を調べるプロセス】
①わからないことが出てくる
↓
②疑問を解消できそうな資料を集める
↓
③集めた資料を選定する
↓
④資料の中から必要な情報を探す
↓
⑤読んで内容を理解する
今の時代、上記のプロセスの②③④は検索エンジンが代わりにやってくれます。
知りたい言葉を入力すれば、その答えが載っていそうなサイトの中から優先度の高いものを順番に並べてくれるわけですからね、手間はほとんどかかりません。
私が学生だった頃、ひと昔前は5段階のプロセスをすべて自前で行わないといけませんでした。
図書館に行き、資料を集め、それらを全て読み、わからない言葉は辞書で引き、読む過程でわからないことが出たらまた資料を集め…といった感じに手間が何倍もかかりました。
ですが、手間がかかることは決して悪いことではありません。
調べる過程で様々な資料に目を通すので、目当ての情報に関連する別の知識を学ぶことができますし、1つの物事を「複数の資料=視点」で見ることができるので理解度が深まります。
多角的に物事を見る力を養うことは、受験においてもかなり重要で、理系科目の場合にその傾向は顕著になります。
いわゆる難関校に合格する生徒は数学だけが突出して得意なのではなく、数学も物理も化学も全て得意です。
そういった生徒は大抵の場合、様々な資料に触れて様々な視点を知り、自分の知識のレンジを深める練習をしているんですね。
「アナログの頃に戻れ」とは言いませんが、簡単に情報が手に入ってしまう現代だからこそ、情報を解析する能力を養ってもらわなければならないな、と思った次第です。
以上、懐古厨のおじさんの嘆きでした。